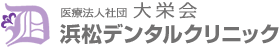歯が溶ける?酸蝕歯について知ろう

こんにちは。
浜松デンタルクリニックです!
皆様は「酸蝕歯(さんしょくし)」という言葉を聞いたことがありますか?
むし歯ではないのに歯が溶けてしまう病気で、近年、患者様が増加しています。
今回は、酸蝕歯とはどのような病気なのか、原因や注意点についてお話しします。
酸蝕歯とは
酸蝕歯とは、食べ物や飲み物の酸によって歯の表面のエナメル質が溶けてしまう病気です。
むし歯や歯周病と並ぶ口腔内のトラブルとして注目されており、放置すると歯がもろくなり、さまざまな症状が現れます。
酸蝕歯になると、歯が黄ばんで見えたり、表面がすり減って小さくなったりすることがあります。
特に噛み合わせの部分が削れやすく、食事や会話に影響を与えることも少なくありません。
また、エナメル質が薄くなることで冷たいものや熱いものがしみやすくなり、知覚過敏の症状が出ることもあります。
さらに、歯の表面がツヤを失い、丸みを帯びたように変化することも特徴のひとつです。
酸蝕歯の原因
酸蝕歯の主な原因は、酸度の高い飲食物に歯が長時間さらされることです。
エナメル質はpH5.5以下の環境で溶けやすくなるため、酸度の高い食品を頻繁に摂取すると、少しずつ歯がダメージを受けてしまいます。
たとえば、かんきつ類や酢を使った食品、炭酸飲料、ワイン、スポーツドリンクなどは特に酸度が高く、注意が必要です。
酸味のある食べ物を好む方は、食べる頻度やタイミングに気を付けることが大切です。
また、胃の状態が酸蝕歯に影響することもあります。
逆流性食道炎などで胃酸が口腔内に上がってくると、強い酸性によって歯が溶けやすくなります。
暴飲暴食が続くと、胃の調子が悪くなり、口腔内が酸性に傾きやすくなるため、生活習慣の見直しも大切です。
歯を守るために
酸蝕歯は、気付かないうちに進行し、むし歯や知覚過敏のリスクを高めてしまいます。
しかし、食生活や日々のケアを工夫することで予防することが可能です。
食事の際は、酸度の高い食品を摂った後にすぐ歯みがきをするのではなく、口をすすいでから少し時間を空けて磨くようにしましょう。
また、ストローを使って飲み物を飲むなどの工夫をすることで、酸が直接歯に触れるのを防ぐことができます。
気になる症状がある場合は、早めに歯科医院に相談し、適切なケアを行いましょう。
初診WEB予約
むし歯治療をはじめ、小児歯科・入れ歯・インプラント・セラミック治療・ホワイトニングなど、各種治療に対応。
お気軽にお問い合わせください。